今年はサド没後200年にあたり、本国フランスのパリ、それもオルセー美術館で、この10月14日から、翌2015年1月25日まで、「サド、太陽を攻撃(Sade Attaquer le soleil)」展が開催されています。
パリへ行ってぜひこの目で見たいところですが、あいにく行けそうにもないので、早速カタログを取り寄せてみたところ、辞書並みの大冊が送られてきて、その全ページに過激なエロティスムの作品がこれでもかと連発されているのに思わず唸ってしまいました。
さすがは、この展覧会を企画・監修した、アニー・ル・ブラン(1942〜)、彼女の過激な精神は、いまだに衰えることはありません。
さすがは、この展覧会を企画・監修した、アニー・ル・ブラン(1942〜)、彼女の過激な精神は、いまだに衰えることはありません。
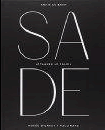
アニー・ル・ブランについては、弊社刊行の「塔のなかの井戸〜夢のかけら」で詳しく紹介したところですが、アンドレ・ブルトンの謦咳に接した最後の世代のシュルレアリストであり、サド、ジャリ、レーモン・ルーセルなどに関する戦闘的評論書やエッセイを多数発表しています。特にサドに関しては、毒抜き作業に走る他のサド研究家連を痛烈に批判した『突然、ひと塊の断絶が、サド』(1986)、『サド、隅から隅まで』(1989)、『倒錯の城』(2010)などを発表、ジャン=ジャック・ポーヴェール版サド全集の序文も書いており、1990年以降の、サドに関する第一人者と言ってよいでしょう。
今回のカタログを閲するに、ドラクロワ、ゴヤ、ロップス、アングル、ロダン、モロー、ベックリン、セザンヌ、フランツ・フォン・シュトゥック、クービン、ピカソ、マン・レイ、デュシャン、ベルメール、マッソン、ウニカ・チュルン、シュティルスキー、トワイヤン、ラウル・ユバック、ジャン・ブノワ、その他作者不詳画などから、人間の欲望と性が露わになった過激で濃厚なエロティスムの作品が一堂に展示されていることが分かります。特に性器や性交、性欲を表現した作品の夥しさは凄まじく、サド以降に描かれた、人間の本質的欲望を抉った作品を基調として、サドによって人類が初めてエロティスムと意識的に向き合い、その本質を自覚し、それを抑圧する神や文明への反逆が生まれ出たことを示して余りある展示となっています。
「人類の幸福、それは無制限な欲望にある」「残虐性、それは人間のエネルギーの本質である」「神という着想を抱いたこと、それは私が人間を許すことができない唯一の過ちだ」など、随所にサドの言葉を散りばめ、他にもフローベールやボードレール、ペトリュス・ボレルなど、人間の欲望の本質を抉った言葉が配置されています。性器や性交の露出作品がパリの中心部のオルセー美術館に夥しい数で展示されているだけでも驚くのに、我々の社会や文明を否定、反逆する言辞をコンセプトとして打ち出していることに、アニー・ル・ブランの明確な意図が感じられます。そしてそれに協力したオルセー美術館長、ギー・コジェヴァル氏の高い知性に敬意を表するとともに、この展示を取り締まらないフランス政府とその社会の成熟度にも驚きます。もし日本のメジャーな美術館で同様の展示をすれば、わいせつ物陳列罪どころか、風俗壊乱、もしくは国家秩序壊乱の疑いで強制的に関係者の逮捕に至ったことでしょう。

フランスに住む友人からも、このサド展を見た感動の連絡が入りました。
そして、アニー・ル・ブランに出会い、彼女が日本の福島の原発の状況に大きな関心を抱いており、人類の行く末を巨視的な目で捕えていることを知らされました。このサド展もまた、人類史という大きな視野から捕えた、まさにサド没後200年の節目にふさわしい画期的なものといえるでしょう。
転じて、日本の貧相な文化状況には唖然とします。
あの「ユリイカ」がサド没後200年を記念してサド特集を刊行しましたが、そこには新訳紹介もなければ、かなり進んでいる本国フランスのサド研究の動きや情報すらない、ましてや第一人者であるアニー・ル・ブランのアの字すらなく、ここ30年の間に発見されたサド関連の書簡や資料、もしくはサドを原作にした過激な発禁本の紹介等々、何もありません。あるのは、もはや食傷気味である1960年代の澁澤龍彦のサド紹介に関する思い出話や「私」のサド観に終始する有り様で、何ら新味のないものでした。
そして、アニー・ル・ブランに出会い、彼女が日本の福島の原発の状況に大きな関心を抱いており、人類の行く末を巨視的な目で捕えていることを知らされました。このサド展もまた、人類史という大きな視野から捕えた、まさにサド没後200年の節目にふさわしい画期的なものといえるでしょう。
転じて、日本の貧相な文化状況には唖然とします。
あの「ユリイカ」がサド没後200年を記念してサド特集を刊行しましたが、そこには新訳紹介もなければ、かなり進んでいる本国フランスのサド研究の動きや情報すらない、ましてや第一人者であるアニー・ル・ブランのアの字すらなく、ここ30年の間に発見されたサド関連の書簡や資料、もしくはサドを原作にした過激な発禁本の紹介等々、何もありません。あるのは、もはや食傷気味である1960年代の澁澤龍彦のサド紹介に関する思い出話や「私」のサド観に終始する有り様で、何ら新味のないものでした。
かつての日本はいち早く海彼の情報や文献を紹介し、それに論考を加えていたものでしたが、コンセプトのないあまりのお粗末さに、「ユリイカ」もここまで堕ちたのかと歎じざるを得ません。文化・芸術に関わる東京大手ジャーナリズムとそれに群がるインテリ層の、知的好奇心なき怠慢・安住ぶりが露骨に表れた一例と言えるでしょうし、ここ30年で、他の先進国に比べて、文化輸入の力量が著しく退化していることを自覚すべきでしょう。もはや私どもも含めた極小出版社が一層奮起しなければならないわけですが、いかんせん資力もなければ、発信力も小さく、忸怩たる思いを禁じ得ない今日この頃であります。